拙HP「戦国島津女系図」の別館…のはず
『Agora』特集「南薩摩 硫黄の道」より。
「島津義久」という単語を歴史の専門誌ではなく、カード会員誌とはいえ一般誌で見るとは思わなかった。余りにもうれしくて無理矢理バックナンバーをもらってしまった。
個人的予想では今後こういう事はもう無いと思うので(涙)
ちなみに特集の内容は坊津を中心とした南薩摩の観光紹介なのだが、坊津を廻る歴史の謎をいろいろと紹介していて興味深かった。坊津と言えば鑑真漂着の地であり、また薩摩藩時代の黒歴史(^^;)密貿易の拠点と言うぐらいしか知らなかったのだが、この記事によると、中国では火薬用の硫黄が出なかったため、この坊津から薩摩産出の硫黄を輸出したらしい。ちなみに火山地帯がある薩摩では、硫黄は取っても取っても減らない資源である。
なお坊津は、古代の地理区分でも地形的に無理のある区分けにされているとか。
そういえば、島津忠良(島津義久・義弘の祖父)の出身家になる伊作島津家はこの坊津を抑えてたんだろうか?
写真で見る坊津は綺麗だったな。こういう話も聞いたからには一度行ってみたい。
坊津に関する資料を展示している輝津館の橋口亘学芸員は、こう解説した。
「戦国末期、薩摩地方を治めていた島津義久が豊臣秀吉に降伏した際、坊津の商人に用立てさせ、銀や白糸、沈香などの礼品を贈っています。これらの貴重な品々は明(中国)との貿易によってもたらされたものであり、坊津から輸出される硫黄によって、取り引きされた物と考えられます。」(以下略)
(p.56)
※下線はばんない補足
「島津義久」という単語を歴史の専門誌ではなく、カード会員誌とはいえ一般誌で見るとは思わなかった。余りにもうれしくて無理矢理バックナンバーをもらってしまった。
個人的予想では今後こういう事はもう無いと思うので(涙)
ちなみに特集の内容は坊津を中心とした南薩摩の観光紹介なのだが、坊津を廻る歴史の謎をいろいろと紹介していて興味深かった。坊津と言えば鑑真漂着の地であり、また薩摩藩時代の黒歴史(^^;)密貿易の拠点と言うぐらいしか知らなかったのだが、この記事によると、中国では火薬用の硫黄が出なかったため、この坊津から薩摩産出の硫黄を輸出したらしい。ちなみに火山地帯がある薩摩では、硫黄は取っても取っても減らない資源である。
なお坊津は、古代の地理区分でも地形的に無理のある区分けにされているとか。
そういえば、島津忠良(島津義久・義弘の祖父)の出身家になる伊作島津家はこの坊津を抑えてたんだろうか?
写真で見る坊津は綺麗だったな。こういう話も聞いたからには一度行ってみたい。
PR
一時期、某掲示板で
「島津は近親婚が多いからキモイ!」
という書き込みを必死になってしていた人がいた。試しに
「じゃ、日本古代の豪族や皇族についてはどう思うのよ?」
と書いてみたら
「古代日本も近親婚が多いんですか?」
…という回答が真剣に返ってきて⊂(。Д。⊂⌒`つ 「ああ、これが噂のゆとりか」…と妙な感心をしたのを覚えていますヾ(--;)
さて、考えてみれば確かに島津家は近親婚が多い傾向がある。
とりわけ義久の代以降は、というか義久自身が近親婚である。これとかこれ
しかし、言い訳しておくが、義久の他の兄弟はここまで酷くはないようだ…
義久のパパ・貴久は先妻が肝付兼興の娘、後妻が入来院重聡の娘だから、戦国大名の政略結婚っぽい。
他の戦国大名を見てみると、確かにこんな半径3mでヾ(--;)嫁を探してくる人の方が珍しいのだ
が、叔父・姪で結婚した例を2件見付けた。それが2つとも南の方に属する戦国大名なのである。
・伊東祐兵(妻は兄・伊東義益の娘)
・長宗我部盛親(妻は兄・長宗我部信親の娘)
2つには共通する事情がある。
兄が元々の正統な世継ぎだったが早世したため、弟がその娘と結婚して代わりに世継ぎになるという物である。但し長宗我部の場合は家臣団から猛烈な反対(人倫にもとるとか)があったらしいですが。
島津義久の例は上記2例とは異なるが(まず第一「叔母甥婚」だし)、拙ブログでもネタにしたこの辺の話が本当であれば、実は危うい家督継承を確実にしていくための結婚であったことは間違いないだろう。
最初の話に戻ると、日本でも古代は近親婚が盛んだったが、時代が下がって行くにつれてだんだん結婚できない範囲が広がってくる
~奈良時代:異母兄弟まで→平安時代:叔父姪、叔母甥まで→鎌倉時代~:いとこまで
家督継承に関わる場合のみという特殊事情はある物の、近親婚が残っていた南日本は、やっぱり古風な習慣が残りやすいのかも知れないなあ。
「島津は近親婚が多いからキモイ!」
という書き込みを必死になってしていた人がいた。試しに
「じゃ、日本古代の豪族や皇族についてはどう思うのよ?」
と書いてみたら
「古代日本も近親婚が多いんですか?」
…という回答が真剣に返ってきて⊂(。Д。⊂⌒`つ 「ああ、これが噂のゆとりか」…と妙な感心をしたのを覚えていますヾ(--;)
さて、考えてみれば確かに島津家は近親婚が多い傾向がある。
とりわけ義久の代以降は、というか義久自身が近親婚である。これとかこれ
しかし、言い訳しておくが、義久の他の兄弟はここまで酷くはないようだ…
義久のパパ・貴久は先妻が肝付兼興の娘、後妻が入来院重聡の娘だから、戦国大名の政略結婚っぽい。
他の戦国大名を見てみると、確かにこんな半径3mでヾ(--;)嫁を探してくる人の方が珍しいのだ
が、叔父・姪で結婚した例を2件見付けた。それが2つとも南の方に属する戦国大名なのである。
・伊東祐兵(妻は兄・伊東義益の娘)
・長宗我部盛親(妻は兄・長宗我部信親の娘)
2つには共通する事情がある。
兄が元々の正統な世継ぎだったが早世したため、弟がその娘と結婚して代わりに世継ぎになるという物である。但し長宗我部の場合は家臣団から猛烈な反対(人倫にもとるとか)があったらしいですが。
島津義久の例は上記2例とは異なるが(まず第一「叔母甥婚」だし)、拙ブログでもネタにしたこの辺の話が本当であれば、実は危うい家督継承を確実にしていくための結婚であったことは間違いないだろう。
最初の話に戻ると、日本でも古代は近親婚が盛んだったが、時代が下がって行くにつれてだんだん結婚できない範囲が広がってくる
~奈良時代:異母兄弟まで→平安時代:叔父姪、叔母甥まで→鎌倉時代~:いとこまで
家督継承に関わる場合のみという特殊事情はある物の、近親婚が残っていた南日本は、やっぱり古風な習慣が残りやすいのかも知れないなあ。
本日、NHKBSプレミアムの「新日本風土記」のネタは「城 十二天守の旅」ということで、現存する12基の天守が紹介されてました。もしかしたら現存する五重塔の数より少ない?
先の戦争で空襲のターゲットにされて無くなった物も多いと記憶してます。名古屋城とか岡山城はそうじゃなかったかな?
姫路城はターゲットにされましたが、何故か全部城をそれたので助かったとのこと。城下町のほうは丸焼けになってしまいましたが。
ふと思ったのですが、大きな領地を持つ大名ほど、幕府に遠慮して天守を建てなかったという通説があるのですが、果たして本当か?ちょっと調べてみました。ちなみに元データはwikipediaなので余り当てにしないようにヾ(^^;)
1 加賀藩(前田家)外様 102万石 金沢城 慶長7年に天守が焼失、以後は再建されず(三層櫓を代用)
2 鹿児島藩(島津家)外様 77万石 鹿児島城 天守は元から無かった
3 仙台藩(伊達家)外様 63万石 仙台城 天守は元から無かった(艮櫓を代用)
4 尾張藩(徳川家)親藩 62万石 名古屋城 五層の天守があったが、戦災で焼失
5 紀州藩(徳川家)親藩 56万石 和歌山城 三層の天守があったが戦災で焼失
6 熊本藩(細川家)外様 54万石 熊本城 五層の天守があった※が西南戦争で焼失
7 福岡藩(黒田家)外様 47万石 福岡城 ? 詳しくはこちら
8 広島藩(浅野家)外様 43万石 広島城 五層の天守があった※が原爆により全壊
9 長州藩(毛利家)外様 37万石 萩城 明治7年(1874年)の廃城令で破却
10 佐賀藩(鍋島家)外様 36万石 佐賀城 享保11年(1726年)火災で焼失
※注 前任の藩主が既に天守閣を造っていた
取りあえず石高上位10位まで見てみました。
意外に天守無しの藩が少ないように思います。元から無かったのは鹿児島藩と仙台藩だけです。その仙台藩でも代用天守を持っているので、鹿児島藩の異様さが目立ちます。
その中でもちゃっかりしてるなあと思ったのが長州藩。関ヶ原の合戦で思いっきり盟主になった上、大減封食らってるのに、しっかり移転先にも天守建ててるという(^^;)しかも、明治になってあっさり取り壊してる…毛利さん、それ観光資源ですよヾ(^^;)
※当時城が飯のタネになるという認識は全くなかったと思われます。
先の戦争で空襲のターゲットにされて無くなった物も多いと記憶してます。名古屋城とか岡山城はそうじゃなかったかな?
姫路城はターゲットにされましたが、何故か全部城をそれたので助かったとのこと。城下町のほうは丸焼けになってしまいましたが。
ふと思ったのですが、大きな領地を持つ大名ほど、幕府に遠慮して天守を建てなかったという通説があるのですが、果たして本当か?ちょっと調べてみました。ちなみに元データはwikipediaなので余り当てにしないようにヾ(^^;)
1 加賀藩(前田家)外様 102万石 金沢城 慶長7年に天守が焼失、以後は再建されず(三層櫓を代用)
2 鹿児島藩(島津家)外様 77万石 鹿児島城 天守は元から無かった
3 仙台藩(伊達家)外様 63万石 仙台城 天守は元から無かった(艮櫓を代用)
4 尾張藩(徳川家)親藩 62万石 名古屋城 五層の天守があったが、戦災で焼失
5 紀州藩(徳川家)親藩 56万石 和歌山城 三層の天守があったが戦災で焼失
6 熊本藩(細川家)外様 54万石 熊本城 五層の天守があった※が西南戦争で焼失
7 福岡藩(黒田家)外様 47万石 福岡城 ? 詳しくはこちら
8 広島藩(浅野家)外様 43万石 広島城 五層の天守があった※が原爆により全壊
9 長州藩(毛利家)外様 37万石 萩城 明治7年(1874年)の廃城令で破却
10 佐賀藩(鍋島家)外様 36万石 佐賀城 享保11年(1726年)火災で焼失
※注 前任の藩主が既に天守閣を造っていた
取りあえず石高上位10位まで見てみました。
意外に天守無しの藩が少ないように思います。元から無かったのは鹿児島藩と仙台藩だけです。その仙台藩でも代用天守を持っているので、鹿児島藩の異様さが目立ちます。
その中でもちゃっかりしてるなあと思ったのが長州藩。関ヶ原の合戦で思いっきり盟主になった上、大減封食らってるのに、しっかり移転先にも天守建ててるという(^^;)しかも、明治になってあっさり取り壊してる…毛利さん、それ観光資源ですよヾ(^^;)
※当時城が飯のタネになるという認識は全くなかったと思われます。
とうとつに 夏も近づく八十八夜
CINIIで「島津」で検索していると恐ろしく古い論文に引っかかったのだが
それに「島津忠良公ご愛用のお茶碗」というのがのっていた。
白黒ながら写真も掲載されていたのだが…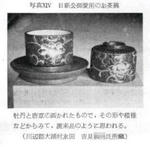
どう見ても形が変なのである
というか、この時代の日本の茶碗ではないことは確実
あえていうとこの時代の中国や朝鮮にもこういう茶碗無いと思うぞ!ヾ(^^;)
そうだな…ダ○ソーで「これちょっと使い勝手悪そうだよなあ」という湯呑みにこういうのがあったような(をーい!)
まあ、忠良の食器と言えばこういう物も「新発見」されたそうなので、もしかしたらもしかするの…か…な???
※この茶碗について何かご存じの方の情報お待ちしてます、かなり真面目に。
参考ネタ 茶道嫌いじゃ忠良おじいちゃん
CINIIで「島津」で検索していると恐ろしく古い論文に引っかかったのだが
それに「島津忠良公ご愛用のお茶碗」というのがのっていた。
白黒ながら写真も掲載されていたのだが…
どう見ても形が変なのである
というか、この時代の日本の茶碗ではないことは確実
あえていうとこの時代の中国や朝鮮にもこういう茶碗無いと思うぞ!ヾ(^^;)
そうだな…ダ○ソーで「これちょっと使い勝手悪そうだよなあ」という湯呑みにこういうのがあったような(をーい!)
まあ、忠良の食器と言えばこういう物も「新発見」されたそうなので、もしかしたらもしかするの…か…な???
※この茶碗について何かご存じの方の情報お待ちしてます、かなり真面目に。
参考ネタ 茶道嫌いじゃ忠良おじいちゃん
元ネタは拙別館ブログのこのネタ
明石屋のしおりによればこうあります
ちなみに高橋元種は江戸初年の大久保長安事件に巻き込まれて改易され、長男が二本松藩士に(※元種の流刑先だった)、二男が鹿児島藩士になってます。高橋家は秀吉の九州御動座に際しては島津氏と共闘したりするなど、仲は悪くなかったんでその関係でしょうな。
ではつづき
没落しただけじゃなくて、武士身分からも転落したのかよ…
あと、種美は聡明なのに何で没落したのか?というつっこみは無しでヾ(^^;)
ちなみに西田町はこちら
続きはこの商品で超有名な問題のエピソード
「このお菓子をお殿様に献上したところ”うまい!で、この菓子の名前は?”と聞かれ、とっさに言ったのがこの名前」
というエピソードが世間に広まっているようだが、明石屋さんによると、とっさに名称変更した訳じゃなくて、島津久光の命により変更した物のようだ。
もっとも、この名称変更には謎があって、「献上した先は大正天皇」説もあるみたい。
明石屋のしおりによればこうあります
この「高橋」って、戦国武将で、元宮崎藩主だった高橋元種の末裔…なんかいな?今を去る240年余り、宝暦十三年島津重豪の代に、高橋八郎種美は(高橋家八代目の嫡子)
ちなみに高橋元種は江戸初年の大久保長安事件に巻き込まれて改易され、長男が二本松藩士に(※元種の流刑先だった)、二男が鹿児島藩士になってます。高橋家は秀吉の九州御動座に際しては島津氏と共闘したりするなど、仲は悪くなかったんでその関係でしょうな。
ではつづき
(○。○)門地資産の豊かな武家であったが中道で落魄し士分を失って
没落しただけじゃなくて、武士身分からも転落したのかよ…
没落した武家が商人に転向しちゃうのはよくある話ですねそう明な種美は常に家運の挽回に心を痛めついに商法を志し餅菓子の独創に成功し意外に好評を得た、
あと、種美は聡明なのに何で没落したのか?というつっこみは無しでヾ(^^;)
商人へのトラバーユは見事に成功したようですが、余りにも成功しすぎて模倣品が続出したようですね(^^;)当時重豪公の盛んな頃で、公が歌舞伎をへいして西田町の西田座に上演せしめたが種美はこの機をつかみこの菓子を売り出し大いに人気を呼んで忽ちにして家運を振作した、それから市中に之れを做って売り出す物が多くなり今日に至ったのである。
ちなみに西田町はこちら
続きはこの商品で超有名な問題のエピソード
「春駒」への名称変更に関してはその形態が馬の一物に似ているというので「うまんまら」と称せられて明治末期頃までもその名前は伝わっていたがそれよりずっと以前久光公が、指宿二月田温泉に清適の折り偶々この茶菓を供したところが「そんな呼び名は女共の前などでは悪いから春駒と呼べよ」との命名が成り立ったというのである。
「このお菓子をお殿様に献上したところ”うまい!で、この菓子の名前は?”と聞かれ、とっさに言ったのがこの名前」
というエピソードが世間に広まっているようだが、明石屋さんによると、とっさに名称変更した訳じゃなくて、島津久光の命により変更した物のようだ。
もっとも、この名称変更には謎があって、「献上した先は大正天皇」説もあるみたい。

